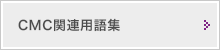【アクテムラとわが研究人生 vol.35 成功体験を社会に還元】
2025.04.29
中外製薬史上初の栄誉の受賞

TEPIAハイテク・ビデオコンクールに出展した「抗体医薬が拓く免疫難病克服への道─IL6と関節リウ マチ」が
「映像文化製作者連盟会長賞」を受賞し、受賞者を代表してあいさつする筆者。

映画の一場面で、コラーゲン関節炎マウスの後肢関節炎症部位における激しい 血管新生像を示している(右図)。
左図は正常関節部
私は2004年8月末に定年退職した後もプロフェッショナル契約社員として5年間、そして顧問としてさらに2年間の勤務を続けた。その間、製造承認申請に係る資料作成、審査当局の照会事項に対する回答案の作成、そして、承認取得後はアクテムラの市場導入・展開に向けての学術関連資料の作成業務などを支援した。前回述べたようにアクテムラが関節リウマチ治療薬として適応拡大の承認を得たのは08年のこと。それまでに、レミケードとエンブレルがそれぞれ02年、05年に、そしてヒュミラが08年にアクテムラにわずかに遅れて発売された。
これらのバイオ医薬品はTNFαを標的とする薬剤なので、IL6を標的とするアクテムラとは明らかに異なる特徴を有しているのであるが、関節リウマチを治療するバイオ医薬品として同種同効薬であると位置付けられ、市場での差別化をどのように打ち出してマーケットでシェアを伸ばしていくのか大きな課題となった。このため、私は各支店の営業活動支援のため、北海道から九州まで全国各地を訪れ、研究会や勉強会、あるいは医局での説明会などで講演し、アクテムラの科学的理解を深めるための活動を行った。また、薬剤の特徴が一目で分かるような色刷りの制作指導もした。また、岸本先生と共著で英文のレビュー論文も数報書いて、アクテムラのユニークな作用特性、特にTNFα阻害薬との違いを意識して世界中にアピールした。
一方、相当の時間を費やした仕事は、プロモーション映画製作への協力・指導であった。映像を製作した桜映画社は、社内に実験室を備え、細胞培養や動物実験をする設備も有し、ライフサイエンス分野に強みを有していた。関節炎を発症したマウスの膝関節部位での新生血管形成の様子や関節骨の破壊像などを実体顕微鏡下で連続撮影することに成功した。作品は、リウマチ関連学会の展示会場ブースで放映され、参加者から好評を得た。科学映画祭(TEPIAハイテク・ビデオコンクール)に出展し優秀賞を受賞した。大きな喜びと達成感を味わうことができ、貴重な体験となった。
大学の同じ研究室の出身で科学技術振興機構(JST)に勤務していた知人の紹介で05年にJST産学連携課の事業の1つである「A-step」の課題評価委員に指名された。私のような者がそんな大役を引き受けていいのかと若干ちゅうちょしたが「アクテムラの開発者としてぜひよろしく」と依頼されて引き受けることにした。新たに生まれた日本医療研究開発機構(AMED)にこの事業が取り込まれた現在でも継続して委員を務めており、新薬創出を目指して挑戦する研究者に対して、死の谷をどう乗り越えればいいのか、その方法について良いアドバイスを提供し、私の使命を果たしたいと思っている。
一方、09年に始まったJSTのCREST(現AMED-CREST)「慢性炎症」の専門領域アドバイザーの一員としての務めも担ってきた。アドバイザーは私を除いて全員アカデミアの先生方であるので、学問的な専門知識は到底及ぶところではないが、私の役割は、アカデミアの基礎研究の成果をどのようにして医薬品開発につなげていけば良いのか、企業での研究開発経験者としてアドバイスすることだと心得てここまで何とか務めを果たしてやってきた。この事業は8年間の期限が設けられており今年が最終年となっている。
このような活動をしている傍ら、学会などの学術集会や大学からアクテムラの成功体験を語ってほしいという要望を受けることもあり、このような依頼を積極的に承諾し講演を重ねた。行く先々で高い評価を頂き、会を主催した先生方からありがたい感謝の気持ちを言っていただいた。大変感動を受けたのは、受講した大学院の学生の多くから「大杉先生の講義に感動し、自分の将来を見つめ直す機会になった」というような感想文を見たときである。また、「アクテムラ誕生にたどり着いた紆余曲折の道程を知り、“すごい人”」だとたたえられると、これまでの長い苦労が報われた気持ちになり感激のあまり目に涙を浮かべながら読むこともしばしばである。
このような活動を通して、退職後の自分がすべき仕事、あるいは果たすべき役割がだんだん見えてきた。それは、アクテムラの成功体験を生かして社会貢献できればという思いである。自分にしかできないことがあると知ったのである。私を望んでくれるなら、喜んでその依頼をお引き受けしてお役に立ちたい。どこであろうと出掛けていって講演する。イノベーション創出(新薬創出)に関わる原稿の執筆依頼であればそれを承諾して原稿を提出する。今ではそのような活動が自分自身に達成感と充実感をもたらし、元気の源になっている。
初出:日経バイオテクONLINE 2017年5月22日掲載。日経BPの了承を得て掲載