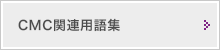【アクテムラとわが研究人生 vol.34 中外製薬史上初の栄誉の受賞】
2025.04.22
中外製薬史上初の栄誉の受賞

日経BP技術賞を受賞者を代表して授与される筆者。

日本薬学会創薬科学賞を受賞したことが、中外製薬の社内報で報じられた
アクテムラが製造販売承認を受けたのは、定年退職して1年後の2005年だったことは前述した。適応症はキャッスルマン病で、日本に100人から150人の患者さんしかいない希少疾患である。薬価は原価計算方式によって決められるので赤字にはならないが、大きな収益は望めない。2003年3月に開催された社内会議において、私がGPL(グローバル・プロジェクト・リーダー)の立場で「製品化提案」の内容を説明した。最後の最後の会議まで承認申請の是非をめぐって議論が交わされた。結局、可決に至ったのは、医師、患者らの強い要望に応えたということと、近い将来、関節リウマチ治療薬として適応拡大の申請が行われる公算が高かったことが大きな原動力となった。すなわち、この段階でCMC関連の審査を通過しておけば、次に関節リウマチへの適応拡大の申請を行った際、その分、審査期間が短縮されるともくろんだのである。
キャッスルマン病は1956年に初めて報告された良性のリンパ増殖性疾患である。リンパ節腫脹、肝脾腫を伴った全身倦怠感、発熱、体重減少、食欲不振などの諸症状が表れ、検査値異常としてCRP、血清アミロイドA、フィブリノーゲンなどの急性期蛋白の上昇、貧血、血小板増多、血沈の高進、高γグロブリン血症、低アルブミン血症などが認められる。1989年、大阪大学の吉崎和幸先生らによってリンパ節局所で多量のIL6 が産生されていることが報告され、これらの異常は、IL6によって引き起こされることが明らかにされた。2次性アミロイドーシスや間質性肺炎など致死的な疾患を合併し、また、患者の約20%が悪性リンパ腫に移行する。適切な治療法の無い難治性疾患であったが、アクテムラの誕生は劇的な治療効果をもたらし、病苦に悩む患者さんにとって大きな福音となっている。
思い出すのは、研究開発の打ち合わせで、各地の病院を訪れた際、臨床医の先生方から受けた相談である。「自分が受け持ちのキャッスルマン病の患者が重篤な状況に陥っていて、もはや治療の手立てを全て失い、後はアクテムラの注射以外の選択肢が無い。何とかして使えないのか」と訴えられる。しかし、たとえ救命目的であったとしても未承認薬の提供は薬事法により禁じられているので、製薬会社としてはどうしようもないのである。断腸の思いでお断りするしかすべは無かった。今アクテムラを投与すれば救命できる可能性があるのにと、患者さんやご家族の心中を思い、社会の理不尽さにやるせない気持ちになることしきりであった。
発売した翌年の06年、第16回日経BP技術賞を受賞する。ホテルオークラで行われた授賞式での審査委員長による審査経過報告によると、「日本初(発)の抗体医薬であること、そしてキャッスルマン病にとどまらず、関節リウマチや全身性エリテマトーデス(SLE)をはじめとする難治性自己免疫疾患に対しても適応が拡大することが期待できる薬剤である」ことが受賞理由だった。受賞自体は大変うれしかったが、少々複雑な思いもあった。実はその時、私は周りの評価として、「アクテムラが抗体医薬である」ということに注目が集まり過ぎるのが嫌だった。それよりも「アクテムラは世界で唯一無二のIL6阻害薬であり、“不治の病”といわれた難病中の難病に画期的な効果を有する医薬品である」ことを高く評価してもらいたいという気持ちが強かったからである。それが、たまたま抗体であったと考えてほしかったのである。
続く07年には、平成19年度日本薬学会創薬科学賞を受賞する栄誉に浴した。富山市で開催された日本薬学会総会において、授賞式の後、受賞者を代表して記念講演を行った。中外製薬史上初の栄誉となり大変に大きな感激を覚えた。この賞を頂くということは、文字通り授賞にふさわしい優れた新薬を創出したことを日本薬学会に認められた証しであり、薬学出身の製薬企業内研究者としては何としても手にしたいと思い続けていた憧れの賞であった。ただしかし、このタイミングではキャッスルマン病治療薬として製造承認を受けたばかりであり、自分としては関節リウマチ治療薬としての適応拡大承認が得られた後に応募しようと考えていた。しかしながら、竹田泰久さん(前出の免疫研究室の初めての後輩)の強い勧めによって急きょ締切日ぎりぎりの応募を決意したのであるが、人生で最高の栄誉に浴することになり、「持つべきものは良き後輩」と思う。推薦者は神戸学院大学の真弓忠範学長(元大阪大薬学部教授)で、受賞講演の司会の労も執っていただいた。真弓学長は、大学時代の同じ研究室の3年先輩で、3年間にわたり公私共に大変お世話になった先生である。受賞にちなんでアクテムラの研究開発について紹介した記事をファルマシア誌に寄稿してくださった(43,469,2007)。
その後もアクテムラは、日本薬学会から大変高い評価をしていただき、学会が発行する高校生向けの小冊子「これから薬学をはじめるあなたへ」の中の「日本で開発された画期的なくすり」欄に、これまでの5種類の医薬品と肩を並べて6番目に加えていただいている。また、2012年発刊の「ファルマシア50年史」には、年表の中にアクテムラの発売年が記されていて感激した。他にはスタチン系脂質異常症治療薬の基になったコンパクチンの発見年、ニューキノロン系抗生物質と認知症治療薬「アリセプト」(ドネペジル)の発売年が記述されているのみなので、日本の新薬開発史上極めて大きな業績を残したと評価されていることをあらためて認識し、私の誇りとしている。
また、2013年のゴールデンウイークの特集号として週刊ダイヤモンド社が発刊した「くすり激変」と題した特集では、2万5000分の1をつかんだ男として紹介されたし、中外製薬と大阪大が産学連携厚生労働大臣賞を授与されたときには、研究開発を先導した「旬の人」として共同通信社から全国各地の新聞に発信され掲載された。講談社から出版された「新薬に挑んだ日本人科学者たち」にも、岸本先生と共にアクテムラの開発者として取り上げられている。
私の手元に1つのメモが残っている。2012年11月に大阪府中央区道修町にある「くすりの道修町資料館」の2階展示室の壁に貼ってあったパネルから書き写したものである。科技庁科学技術政策研究所「第7回技術予測調査」から抜粋・引用された資料で、そこには治療困難な疾患の治療法の進歩についての未来予測が記されていて、「2021年に慢性関節リウマチなどの自己免疫疾患が完治可能となる」とあった。ちなみに、癌の免疫療法、遺伝子治療法が普及するのは2018年、転移を防ぐ有効な手段が実用化されるのは2017年、アルツハイマー病を完治させるのは2020年と予測されている。従って、関節リウマチの治療薬の開発がそれらの疾患より困難であると考えられていたことが分かる。関節リウマチに限って言うならば、まだ完治には至っていないものの、この技術予測は95年に発表された調査結果(日本薬史学会編、「日本医薬品産業史、169ページ、薬事日報社」)であり、わずか十数年という短期間のうちに予測を10年以上も上回るスピードで治療薬の開発が進展したといえる。
本連載を続けて読んでいただいている読者はお気づきかもしれないが、文中に「関節リウマチ」と「慢性関節リウマチ」の2つの病名が使われている。それは03年頃に「慢性」の2文字が病名から削除されたからである。多くの若い女性に発症する疾病なので、その病名を告げられたときの「もう治らない病気にかかったのだ」という絶望感を与えるのは、あまりにも悲惨で残酷であるとの配慮が働いたからである。このような難病中の難病の治療薬の開発に挑戦し、患者の福音となるような有効な医薬品アクテムラの開発に携われたのは大変幸運で、まさに研究者冥利に尽きる。
初出:日経バイオテクONLINE 2017年5月15日掲載。日経BPの了承を得て掲載