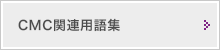【アクテムラとわが研究人生 vol.27 仰天の売り上げ予測】
2025.03.04
仰天の売り上げ予測

臨床投与量の予測(筆者直筆資料の1ページ目)。
他社が開発中の4種類の抗体医薬の1回投与量は5mgから100mgの範囲であることが論文などの公開資料で判明。
ここからアクテムラの生産量と生産コストが概算された

発性骨髄腫を対象疾患とした開発提案書ドラフトの市場性に関するペー ジ。
薬価の参考になるものは、86年に臓器移植拒絶阻止薬としてFDAから製造承認されたオルソクローン(マウス抗OKT3抗体)ただ1つしかなかった。
1回投与量が5mgで500ドルだったので、これを参照し薬価を1回10万円と仮定。
月5回から10回投与で、5000人に使用されれば日本だけでも年商は300億から600億円になるとした。
可能性のある適応症としては9疾患が挙げられている。鉛筆で書き足してあるように産婦人科や小児科領域での応用も議論された
医薬品の開発を進めるか否かを決定する際、上市(発売)されたときの売上高を予測するものである。どんな効果があり副作用がどうなのか全く予想もできない段階で数値を出すのは、革新的医薬品を研究開発する身にとっては実にばかばかしいことに思えた。その時点で販売されている既存品の売上高合計金額を市場規模とし、それらと比較してどの程度のシェアを獲得できるのか予想して、その製品の売上高を算出する──つまり、革新的医薬品の登場によって市場規模が拡大することを全く計算に入れないのである。従って、発売前の売上高は実際よりも小さくなりがちだった。
しかし、研究開発本部長の梅本賢次さんが、抗IL6受容体抗体PM1の開発を決議した1990年頃に非公式に示したMRA(後のアクテムラ)の売り上げ予測は、それとは違っていた。何と1兆円を超えるというのだ。
当時、MRAはそれまでの動物実験や患者由来の細胞を用いたin vitro試験の結果から、多発性骨髄腫のみならず、全身性エリテマトーデス(SLE)、関節リウマチ、多発性硬化症、IgA腎症、ある種の固形癌など、有効な治療薬の無い複数の難治性疾患に対しても有効性が期待されていた。いずれの疾患においても競合品がほとんど存在しない画期的な医薬品となるのでシェアの獲得率は極めて高くなり、売上予想額を合計するとそうなったということである。大方は、会社の年間売り上げの何倍にも当たるあまりにも大きな数字にあぜんとして声も無かったが、私たちにとっては大変痛快であった。余談だが、2015年に「ヒュミラ」や「レミケード」などが1兆円前後の売り上げを達成したことを思えば、あながち絵空事ではなかったといえよう。
ただ、市場規模の話は薬価制度を抜きにしては語れない。イノベーション創出には時間もかかればお金もかかるが、自由薬価制度ではなく公的薬価制度を採用している我が国では、投資を全て価格に反映できるわけではない。新薬の薬価の算定は類似薬効比較方式を基本とし、画期的な新薬の場合には補正加算を行う仕組みになっているが、90年代初めまでは数%といったほんのわずかの加算しかなく、その後、加算の比率は引き上げられてはいるものの、これまでに大きな加算が認められた事例は非常に少ない。すなわち、イノベーションの価値に見合う価格設定制度になっていないのである。
画期的発明に対する評価が乏しければ、新薬創製という大変にリスクの高い、それ故に大きな勇気を必要とする難業に挑戦するためのモチベーションがわき出てこない。米国では、製薬企業が新薬の価値に見合う価格を自由に設定でき、そこで得られた利益が次なる画期的新薬の研究活動に有効に活用されるというサイクルがうまく回っている。日本の薬価制度が現状のままでは、製薬企業における画期的新薬の発明意欲は高まりにくいのではないか。ひいては、革新的新薬を発明した研究者が正当な評価を受けられなくなり、その結果、危険を冒してまで大きな冒険を成し遂げようとする者も現れにくくなるのではないかと心配している。
研究開発段階で開発を進めるか否かを決める意思決定の方法に関して、もう1つ述べておきたいことがある。96年だったと記憶しているが、中外製薬では、上市した場合の売上高の予測に加え、事業性評価という名の下に各研究テーマのランク付けが行われることになった。MRAを含め4品目のグローバル開発プロジェクトが走っていたので、ある経営コンサルタント会社の考案した方法に倣って各プロジェクトを評価し、その結果から開発の優先順位を決定しようというのである。その方法では、患者数や薬価から導かれた市場サイズ、それから既存品と比較して期待できるシェアなどの評価要素に加え、成功確率の予想という評価項目があった。研究開発ステージの節目節目にハードルを設け、例えば非臨床試験から臨床第I相試験に進む時点で、成功確率は何%かとプロジェクトチームのリーダーに問うものだ。この評価を受けることになったあるプロジェクトリーダーが、評価担当者からの質問に対して、「成功確率は0から100%です」と答えた。私は、「言い得て妙」だと、感心したのを今も鮮明に覚えている。なぜなら、画期的な新薬の開発とはまだ誰も足を踏み入れたことのない真っ黒で奥深い森の中に歩を進めることなのだから、目の前の難関を乗り越えてさらにその先に進めるのかどうかなど「神のみぞ知る」なのである。
初出:日経バイオテクONLINE 2017年3月21日掲載。日経BPの了承を得て掲載