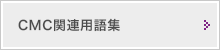【アクテムラとわが研究人生 vol.26 「世界広し」といえども】
2025.02.27
「世界広し」といえども

マウスで作製した抗ヒトIL6受容体モノクローナル抗体(PM1)をCDR移植法という遺伝子工学的手法を用いてヒト化した抗体を多発性骨髄腫治療薬として開発する研究方針が具体化して行く中、PM1を上回る強い活性を有する抗体を見いだそうと、小石原さんらチ-ムメンバーが可溶性IL6受容体で免疫したマウスから多種類のモノクローナル抗体を樹立し、活性を比較したが、PM1よりも優れた抗体は見つからなかった。
in vitroではPM1よりも数倍強い阻害を示してもin vivoではそうはいかなかった。その理由は今もミステリーのままである。ビギナーズラックと言うのだろうか、薬物スクリーニングの際にしばしば経験することであるが、最初に見つけられた化合物が最善であることも多い。PM1を上回る活性を持ったモノクローナル抗体を作製することができなかったが、同程度の活性を示した抗体は何種類か樹立されたので、その中からAUK12-20を含む3種類の抗体をバックアップ用候補抗体とすることを決めた。PM1を加えていずれもが、それぞれ認識エピトープを異にするものの中から選抜した。研究所長の貞広隆造さんのアドバイスもあって、もし、先々PM1に何らかの問題が生じたときのために準備しておこうということにした。
1990年新年早々の1月11日、私は、貞広さん、研究第3部長の松野隆さんと3人で大阪大学細胞工学センターに岸本先生を訪ねた。中外がIL6, 並びにIL6受容体に対するマウスモノクローナル抗体のキメラ化、およびヒト化抗体を多発性骨髄腫の治療薬として開発研究を進めることを伝えるためである。
先生からの合意が得られたので、早速、同年2月17日から3月3日にかけてヒト化抗体の作製を委託できる相手を探し出すため貞広所長と共に世界を一回りして調査した。名だたる大手製薬企業数社を訪問して相互に情報交換し議論した。世界広しといえども、さすがにヒト化技術を有する製薬企業はヨーロッパにも米国にも無く、ただ1つ米国シリコンバレーにあるベンチャー企業米Protein Design Laboratories(PDL)社だけが共同研究パートナー候補となった。しかしその後、これとは別に、英王立医学研究所(MRC:Medical Research Council)内に設立されたMRC Collaborative CenterというMRC傘下の関連施設(MRCCC)でマウス抗体のヒト化技術の指導を受けられることが分かった。
PDL社はQueen’s Patent、MRCはWinter’s Patentと呼ばれるヒト化技術特許をそれぞれ保有していた。結局、MRCとの共同研究に踏み切った決め手となったのは費用が安いことと中外の研究員を受け入れてくれたことだった。本技術の日本市場への仲介権利は住友商事が独占的に保有していた。契約締結や現地案内など色々とお世話をしていただいた。
90年6月8日開催の経営会議において、マウスで作製した抗ヒトIL6受容体モノクローナル抗体をCDR移植法という遺伝子工学的手法を用いてヒト化した抗体を多発性骨髄腫治療薬として開発研究を推進することが決議された。また、ヒト化に関する共同研究のパートナーとしてMRCCCを最有力候補とすることについても併せて承認された。この決定に伴って、研究テーマ名BF検体は、開発コード名「MRA」に変更された。Myeloma Receptor Antibodyの頭文字を取って私がMRAと命名した。
MRCとのヒト化抗体特許のライセンス契約は90年7月30日付で締結され、中外は世界的な非独占的商業実施権を獲得した。対価として、イニシャルペイメントや売上高に対して一定のロイヤルティーを支払うといった内容だった。これは当時の英Margaret Thatcher首相の外貨獲得政策(英国で開発された知的財産を海外に導出することで外貨を獲得する狙い)の一環と聞いた。そして同年8月14日付で共同研究契約が締結され、プロジェクトは大きく前に動きだした。
共同研究契約に基づき、中外からMRCに2人の研究員を派遣した。2人は私と同じ新薬研究所研究第二部の所属で、細胞の培養や生化学などのエキスパートである佐藤功さんと、既に分子生物学の高い技術と大きな成果(G-CSF遺伝子クローニングの中心的人物の1人)を有していた土屋政幸さんである。会社からIL6受容体に対するマウス抗体を、抗体工学的手法を用いてヒト化するという挑戦的な研究課題を命じられ、90年9月17日、MRCに赴任した。
2人は、それに先立つ8月7日、派遣に備えて自分たちの住むアパートを探し、住居を確定するためにロンドンに出張したので、私は彼らに付き添った。現地の不動産屋さんの紹介物件を何軒か見て回り、無事にそれぞれ気に入った家が見つかった。3人でテムズ川の遊覧船に乗ったが、ぽかぽか陽気で2人は船上でウトウト。私はミノルタの一眼レフで写真を撮ったのだが、自動露出計の故障で真っ黒気。苦い経験を思い出した。
後日談であるが、佐藤さんの家はトラブル続きだったらしく、広い裏庭のある立派な一軒家であったが、エアコンの調子が悪いとかで大家さんに掛け合ってもなかなか修理してくれないし、日本とのカルチャーショックを味わったと聞いた。
我々3人はこの機会を利用して、8月9日と10日の両日、第1回目の中外-MRCCC共同研究ミーティングを開催した。協議の結果、PM1, AUK12-20を含む4種類のモノクローナル抗体について、それぞれの可変領域のcDNAをクローニングし、1次構造決定後、その中から3種類の抗体を選抜してコンピューターによるヒト化抗体の構造デザインニングを実施し、その結果に基づいて最終的に1種類の抗体に絞り込み、キメラ化とヒト化抗体遺伝子を構築しCos1細胞で発現させるという研究手順で合意した。
第2回合同ミーティングは、91年2月に予定されていたが、湾岸戦争のために急きょ中止となり、あらためて4カ月後の6月26日、27日の2日間MRCCCでの開催となった。貞広さん、福井さん、秋元利夫さんと私の4人が参加した。研究は計画通り順調に進展し、4種類全てのモノクローナル抗体の可変領域cDNAのクローニングが終了し、いずれのキメラ抗体(ヒトIgG1)にも活性が認められたと報告を受けた。さらにPM1については、ヒト化が進行中であり、マウス抗体の約3分の1の活性を有するバージョンが得られており、さらに活性を上げるべく構造を改良中とのことであった。秋元さんは、結晶構造学の専門家としてMRC側の同じ専門領域の研究者と一緒にコンピューターの画面上にヒト化抗体の立体構造を映し出し、画像を回転させながら観察し、高活性を保持した抗体の構造設計・最適化に取り組んだ。
我々は、マウス抗体の骨髄腫細胞増殖抑制作用と物理学的性質について報告した。会社側ではPM1には若干の不安材料があることから、バックアップ抗体としての第2番目の抗体のヒト化を進めることが重要であると判断していたので、その旨を伝え協力を要請した。その結果、共同研究期間を半年間、すなわち92年3月まで延長することで合意した。その時点ではAUK12-20を有力視しているが、今後さらにもう少し検討を加えるので、最終決定は2番目の抗体のヒト化実験が開始される8月初めまでに通知すると約束した。
92年4月18日、土屋、佐藤の両君は1年7カ月の滞在を終えて帰国した。MRCCCから提示された当初の工程表では1年間で第1候補となる抗体のヒト化を完成する予定であったが、約9カ月でヒト化抗体の作製を完了した。そして、引き続きバックアップ用抗体AUK12-20のヒト化作業に取り掛かり、これも半年で完成することに成功した。マウス抗体の活性を100%保持したままヒト化に成功したのは世界で初めての快挙であった。しかも、彼らは先方から技術指導を受けるだけにとどまらずMRCの既成技術をさらに改善したという逸話も残された。土屋さんは後に、当時抗体工学においてはMRCと米国研究者とで激しい研究競争が繰り広げられており、日本の出遅れを痛感したと記している(2002年)。
このヒト化PM1抗体がアクテムラであり、その後に前臨床試験、臨床試験へとステージアップして開発が進められていく。
初出:日経バイオテクONLINE 2017年3月13日掲載。日経BPの了承を得て掲載