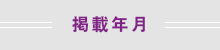【アクテムラとわが研究人生 vol.12 カルフェニールの育薬研究】
2024.11.19
カルフェニールの育薬研究

1985年頃の著者。中外製薬綜合研究所第二本館第三研究室居室にてス
カルフェニールの臨床開発は順天堂大学医学部膠原病内科の塩川優一教授を中心に進められた。初めて先生にカルフェニールの概要を説明した際に、先生が私の考えを受け入れて、ゆがんだ免疫のバランスを是正できる「免疫調節作用」という斬新な作用機序に理解を示していただくことができて本当にほっとした。当時としては全く新しい概念であり、専門家筋に受け入れられるのかどうか半信半疑だったからである。カルフェニールが臨床第I相試験、第II相試験と段階を踏んで、全国規模での多施設二重盲検試験まで進んだのは、新しい概念を許容し挑戦的な試みを受け入れた塩川先生の抱擁力と、リウマチ学界の重鎮として自ら先頭に立って道を切り開いた指導力と行動力に負うところが大きかったと思う。
1981年に私が帰国してしばらくすると、カルフェニールの関節リウマチを対象とした臨床第III相試験が成功裏に終了し、製造承認申請の準備に入った。革新的新薬として世の注目を集めており、会社としても大きな期待を寄せていた。そこで、私に与えられた帰国後の主な業務の1つはカルフェニールの育薬研究だった。
「育薬」とは、読んで字のごとく、薬を育てるという意味である。すなわち、市販後の薬剤が適正に使用され、安全で有効に治療に用いられるように、その薬剤の作用機序や特性に関する実験証拠を創出する研究を指して育薬研究と呼んでいる。
当時の研究本部の組織では、新薬研究所とは別に応用研究所があり、育薬研究は応用研究所の職務だった。しかし、カルフェニールについては新薬研究所が担当していた。私は新薬研究所の第三研究室の所属であった。私にカルフェニールの話を持ち掛けた先述の中野さんは、第八研究室の所属であったが、それ以来私の研究室に入り浸りになっていた。彼は、私とほぼ同じ時期、すなわちカルフェニールが臨床試験に入った頃に東京大学薬学部に留学した。糖鎖を認識するレクチンに関する研究で成果を上げ、学位を取得した。会社に戻ってからも、私の研究室に頻繁に出入りしてカルフェニールに関する研究を続けた。
カルフェニールは、免疫抑制作用も無く、抗炎症作用も無いのに、ラットアジュバント関節炎を抑制するのはなぜなのか? その謎を解く手掛かりは、抑制性T細胞の活性化作用にあるとの仮説を裏付けるための研究に取り掛かった。留学以前の話に遡るが、76年に九州大学の古賀敏生教授のグループによって、ラットアジュバント関節炎は、X線照射や抗リンパ球抗体の注射により症状が悪化するが、胸腺細胞を移入することで元に回復することが明らかにされ、X線に感受性で短寿命性の抑制性T細胞によって制御されていることが示唆された。そこで我々は、リンパ球に対するウサギ抗体を注射したところ、カルフェニールによる関節炎抑制作用が消失した。また、胸腺を摘出したラットではカルフェニールは関節炎を抑制しないことも分かった。これらのことから、カルフェニールは、胸腺由来の抑制性T細胞を介して作用を発揮する可能性が強く示唆された。渡米する直前のことだったので論文作成に費やす時間が無かったのだろう、帰国後の83年の論文発表となった。
私は帰国後間もなく新薬研究所第三研究室免疫研究グループのリーダーとなった。82年に片桐晃子さん(旧姓上野)、83年に小森利彦さん、85年に三原昌彦さんと内山也寸志さんが研究グループに加わった。
私は、中野さんや山下さんと共同で、これまで残されていた重要な課題であったカルフェニールの抑制性T細胞の活性化作用に関して新たな取り組みを始めた。脾臓リンパ球を試験管内で、コンカナバリンAで刺激すると抑制性T細胞が誘導されることが既に他のグループから報告されていたので、この実験系を用いることにした。そして、自己免疫疾患のモデルであるNZB/NZWF1マウスでは、加齢に伴って抑制性T細胞の機能が著しく低下すること、並びに、カルフェニールの投与で低下状態の抑制性T細胞機能が明らかに増強されることを見いだし論文発表した(83年)。
その後、片桐さんが加わってから、この研究をさらに発展させ、カルフェニールの免疫調節作用がNZB/NZWF1マウスに認められるポリクローナルB細胞活性化現象の抑制につながり、その結果、抗DNA自己抗体産生の減少をもたらすことを強く裏付ける大きな成果を上げた。論文公表(International J. Immunotherapy、1985)したときには、大きな反響があり、欧米の大手製薬企業十数社からカルフェニールのサンプル提供依頼が相次いだ。
小森さんに担当してもらったのは、カルフェニールの免疫調節作用についての研究だ。小森さんはヘルパーT細胞、抑制性T細胞をそれぞれ選択的に抑制するような実験手技を開発した岡山大学の山本格教授の研究室の指導を受け、カルフェニールのユニークな免疫調節作用を明らかにしてくれた。すなわち、マウスを体にぴったりな容器に身動きが取れないように拘束してストレスを掛けるとヘルパーT細胞の活性が特異的に低下するが、カルフェニールを投与することにより低下したヘルパーT細胞の機能が正常なレベルまで回復することを証明した(87年論文発表)。
一方、山本先生らは、コルヒチンを注射されたマウスでは抑制性T細胞の機能が特異的に低下するが、カルフェニールを投与することにより低下した抑制性T細胞の機能が回復することを証明していた(82年)。全く同じ実験モデルで小森さんらは、山本先生らが用いた抗原とは異なる別の抗原を用い、カルフェニールの抑制性T細胞機能活性化作用の再現に成功している(未発表データ、84年)。つまりカルフェニールは、ヘルパーT細胞であれ、抑制性T細胞であれ、機能が低下している方を回復させて免疫機能を正常な状態に戻す作用を有していることを証明したのである。
この一連の研究成果は小森さんの博士論文になった。山本教授は私の大学の4年先輩で、無理を聞いていただき感謝している。ちょうど岡山大学薬学部では博士課程が新設され、1期生が最終年度を迎えていた。そのため、博士課程の1期生と論文博士が同時に誕生するのは不公平感が生じるとの理由で、小森さんへの学位授与はその翌年の89年までお預けになった。
三原さんは、MRL/lprマウスを用いて、カルフェニールによるSLE腎炎の発症抑制効果は、異常なポリクローナルB細胞活性化の改善効果を介して発揮されることを明らかにして論文発表した(87年)。このマウスでは、腫大したリンパ節内の異常T細胞から遊離するB細胞増殖分化誘導因子(l-BCDF)がポリクローナルB細胞活性化を誘起すると考えられており、抑制性T細胞の機能低下が原因ではない。従って、本マウスにおいては、カルフェニールの効果はリンパ腫大を抑制し、l-BCDFの遊離を抑制することでB細胞の異常活性化を阻害する作用メカニズムが働いていると考えられる。
以上の研究を通して、カルフェニールは、ヘルパーT細胞の機能が低下しているときには、免疫を増強回復させ、逆に抑制性T細胞の機能が低下している状態では免疫を抑制し、アンバランスになっている免疫機能を正常状態に戻す、いわゆる免疫調節剤としての性格を有していることが明らかになった。この免疫調節作用を介して自己抗体産生を抑制するのではないかとする我々の期待通りの大変興味深い、そして意義深い実験証拠が蓄積されていったのである。
82年8月1日発刊の「投資経済」誌で、中外製薬常務の佐野肇さんが、「免疫調節剤でリウマチ疾患に効くのは、今のところCCA(カルフェニールの開発コード)しかない」「10月に製造承認申請の予定で、年商100億円台の大型化が予測され、海外数十社から技術提携を持ち込まれている」と述べている。世間ではいつの間にか、「免疫の中外」とはやされるようになっていた。
初出:日経バイオテクONLINE 2016年11月28日掲載。日経BPの了承を得て掲載