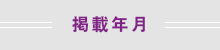【アクテムラとわが研究人生 vol.11 静脈内注射の世界チャンピオン】
2024.11.12
静脈内注射の世界チャンピオン

ヌード遺伝子を導入したニュージーランドマウス

NZB/NZWF1マウスでは、生後早期からB細胞コロニー数が増加していることを示す
実験データ(左から脾臓、リンパ節、骨髄)。
パリで開催された国際免疫学会での発表やJ.Immunologyに掲載された論文に使用した
NZB/NZWF1マウスは、自己免疫疾患であるSLEの優れた実験モデルマウスとして頻用されていた。カルフェニールの有効性も、このマウスを用いて見いだしたことは前述した通りだ。Gershwin博士から最初に与えられた課題は、このマウスのB細胞機能を、コロニー形成法を用いて調べることだった。研究の結果、NZB/NZWF1マウスは、正常マウスと比べ、多数のB細胞コロニーを形成することが分かった。脾臓でも、リンパ節でも、また骨髄でもB細胞異常が観察された。この異常は胎生期から既に認められることから、生まれつきの内因性の異常であると推察された。また、このマウスは無菌状態でも、さらには、胸腺を欠損したヌードマウス(NZB/NZWF1 nude mice)でも、同様のB細胞活性化が認められることから、T細胞や感染の関与は否定的であると考えられた。
この結果は、1979年にThe Journal of Immunology誌に掲載された。これまでの抑制性T細胞の機能低下が自己免疫の原因であるとする学説に一石を投じたものであった。私にとっては高根の花だった免疫領域のトップジャーナルに、いとも簡単に受理される研究を成し遂げる米国の一流科学者の力に驚嘆した。
NZB/NZWF1のヌードマウスは胸腺を欠損し、従ってT細胞が存在しない。このようなマウスを作製するにはマウスの交配を繰り返し行う必要があり、1、2年もの長期にわたり、金銭的にも大変な作業だが、私が渡米した時には既に繁殖が軌道に乗りつつあり、1回の実験に数匹ではあったが使用できるようになっていた。私に与えられた次の課題は、このヌードマウスが自己免疫疾患を発症するのかどうかを観察することだった。
というのもNZB/NZWF1マウスは、生後4、5カ月で自己のDNA成分に対する免疫学的寛容が破綻し、抗DNA抗体を産生するようになる。この自己抗体は、血中のDNAと免疫複合体を形成して腎臓の糸球体の毛細血管に付着する。するとそこで補体が活性化され、好中球が浸潤することで炎症反応が引き起こされて最終的には糸球体腎炎から腎不全に進行し、9カ月ほどで死亡する。では、T細胞が存在しないヌードマウスでも自己免疫疾患を発症するかどうか。それを検証することが課題となったのである。
実験の結果は驚くべきものだった。ヌードマウスでも腎炎を発症し、腎不全を起こして死亡することが観察されたのである。抗DNA抗体の産生もワイルドタイプのマウスと同等に認められたので、自己抗体の産生にT細胞が必須ではないことが分かった。これは世界で初めての実験的証拠であり、問題なく80年にThe Journal of Immunology誌に掲載された。この年、パリで開催された国際免疫学会でこの結果を発表したところ、自己免疫学者の間で1つのトピックとなった。その際、会場内の休憩所で当時大阪大学医学部講師だった岸本忠三先生から「よう頑張ってるようやな」と声を掛けていただいた。私の米国での研究成果にまで気を掛けてくださっていると知って少々驚いたが、とてもうれしかった。
今までに得られた事実を裏付けるためにXid(X-linked immunodeficiency)遺伝子を導入したNZB/NZWF1マウスが樹立された。このマウスはB細胞に欠陥が生じており、免疫グロブリン(Ig)Mは産生するが、IgGクラスの抗体を産生できない。全身性エリテマトーデス(SLE)の発症は、DNAに対するIgG抗体が産生されるからなので、このマウスでは自己免疫疾患は発症しないであろうと予測できた。結果は期待通りであった。
このように、米国で得られた知見はいずれもSLEのB細胞原因説を支持するものであり、これらの事実に基づいて、「B細胞を制御する薬剤が根本的な自己免疫疾患治療薬になるのではないか」と考えるに至った。ただ、米University of California大学 Davis校のキャンパス内を実験室からオフィスまで歩きながら移動中に、Gershwin博士から「どうすれば自己抗体産生を防げると考えるか?」と問われ、「B細胞を阻害すれば良いのでは」と答えたものの「そんなことをすれば患者は免疫不全に陥るだろう」と指摘され、それ以上は反論できなかった。私の新薬創製への挑戦は、まだまだ始まったばかりだったといえる。
Gershwin研究室では、「Dr.大杉は静脈内注射の世界チャンピオン」と呼ばれた。無菌マウス飼育用チャンバー内のマウス、しかも幼若マウスの尻尾の静脈内に注射針を刺す、それもチャンバーに装備されているゴワゴワ・ブカブカの大きなゴム製手袋を通して左手に小さな尻尾、そして右手に1mL用量の細い注射筒を持って割合簡単にやってのけるのを見たテクニシャンが私のことをそう呼んだのが始まりだった。この特殊才能のおかげもあって他の幾つかのプロジェクトにも手伝いに駆り出された。その結果、2年9カ月の滞在中に公表された共著論文の数は10報を超えた。帰国すると、「留学中にこんなに多くの論文を発表した中外研究者はいない」と周囲を驚かせた。手先の器用さのたまものである。
初出:日経バイオテクONLINE 2016年11月21日掲載。日経BPの了承を得て掲載